“超最高”を設計せよ──顧客の心を動かすコクヨ「やる気ペン」開発物語

技術革新は、必ずしも「すべてをデジタルに置き換える」方向で進んでいるわけではない。むしろ近年目立つのは、長年親しまれてきたアナログな体験を、テクノロジーの力でアップデートすることで生まれるイノベーションだ。
その象徴的な例が、アサヒビールの「未来のレモンサワー」である。缶を開けると、中に入った本物のレモンスライスが浮かび上がる──。飲料としての本質は何も変わらない。それでも、開けた瞬間の驚きや高揚感は、これまでのレモンサワーとはまったく異なる体験を生み出した。ここで主役になっているのは最新技術そのものではなく、「美味しいお酒を飲む」という日常的でアナログな行為が、感情レベルでアップデートされている点にある。
同じ構図は、文房具という市場にも起きている。日本の文房具市場は、長らく「横ばい、あるいは微減」という停滞期にある。その中で、120年の歴史を持つコクヨ株式会社が世に送り出したIoT文具「やる気ペン」シリーズは、累計7万台を超える異例のヒットを記録した。
第一の矢となった「しゅくだいやる気ペン」は、市販の鉛筆に取り付けるアタッチメント型のデバイスだ。センサーが筆記量(勉強時間や動かし方)を検知し、書けば書くほどペンに「やる気パワー」が溜まり、色が変化する。そのパワーをスマホアプリへと注ぐことで、すごろく形式のゲームが進んだり、アイテムを収集できたりといった「家庭学習の習慣化」を支援する。
そして第二の矢として登場したのが、「大人のやる気ペン」。コンセプトはそのままに、デザインと機能を大人向けに再定義した。ボールペンやシャープペンシルなど多様な筆記具に装着できるよう小型化され、アプリも資格試験や自己研鑽に励む大人の孤独な努力を支える仕様へと進化。1%の成長を可視化し、同じ目標を持つ仲間とネットワーク上で繋がることで、挫折しがちな大人の学びを伴走する。
単なるアナログ文具のデジタル化に留まらず、親子のコミュニケーションや大人の学習習慣そのものを変容させたこのプロジェクト。その裏側には、新規事業担当者が陥りがちな「技術の罠」と、それを打破するための「4コマ漫画発想法」があった。開発を率いた中井信彦氏の言葉から、顧客の心を動かす新規事業論を紐解く。
技術発の失敗が教えてくれた、新規事業の罠
「コクヨの強みであるアナログ文具にデジタルを掛け合わせ、新しい市場を作れないか」。そんな役員からのお題が、電機メーカー出身で中途入社したばかりの中井氏に降りてきた。
中井氏はまず、1万点に及ぶコクヨ製品の中から「鉛筆」を選んだ。理由は明白だ。コクヨには「キャンパスノート」をはじめ、学習領域において圧倒的なブランドとユーザー接点がある。「書くこと」にデジタルを付加すれば、必ず新しい価値が生まれるはずだ。
しかし、最初の1年間は壮大な空振りに終わる。
当初、中井氏が描いたコンセプトは「見守り(監視)」だった。共働き世帯が増える中、離れた場所にいる親が、子供が机に向かっているかをスマホで確認できる。そんな社会課題の解決を掲げた。
だが、製品化を前に約500名規模の量的調査を行った結果、突きつけられたのは残酷な現実だった。「子供の勉強を見守れていますか?」という問いに対し、大半の親は「見守れている(必要ない)」と回答。そもそも、そんな機能にお金を払いたいという親は皆無に等しかったのである。
「社会課題を、自分の都合のいいように解釈していた」。中井氏は当時をそう振り返る。自社が持つ技術や、世の中のトレンドに引きずられ、顧客が本当に求めている「幸せ」を見失っていたのだ。プロジェクトは、一度白紙となった。
「幸せな顧客」を定義:観察によるインサイト発掘
どん底にいた中井氏を救ったのは、ある本に出会ったことだった。そこには「ビジネスとは、未開の訪問者が、その仕組みを通ることで『幸せな顧客』に変わるプロセスのことだ」と記されていた。
「自分はデバイスを作ることに必死で、顧客が幸せになる瞬間を具体的にイメージできていなかった」。中井氏は、一人の顧客の解像度を徹底的に高める「N=1の観察」に立ち戻ることにした。
30ほどの家庭にお願いし、子供が家で勉強する姿をビデオで撮影してもらった。そこで目にしたのは、想定していた「美しい学習風景」とは程遠い泥臭い現実だった。
描き始めて1分で飽き、鉛筆キャップをいじり、別の遊びを始める子供。それを見て、撮影中にもかかわらず「いい加減にしなさい!」と怒鳴ってしまう母親。 「親は離れた場所から監視したいのではない。目の前の子供にガミガミ言いたくないし、もっとポジティブに関わりたいと切実に願っている。しかし、その手段がないために負のサイクルから抜け出せずにいたのです」
ここで、中井氏の中で「幸せな顧客」の定義が書き換わった。目指すべきは監視ツールではない。「書いて、褒める」というポジティブなサイクルを家庭内に生み出す装置だ。
4コマ漫画発想法:「4コマ目の笑顔」を描けているか?
中井氏が新規事業を構想する際に用いるのが「4コマ漫画発想法」だ。
1コマ目: ユーザーが抱える現状の課題(ガミガミ怒る親、やる気のない子)
2コマ目: 解決策としてのプロダクト(しゅくだいやる気ペン)
3コマ目: プロダクトを使ったアクション(ペンが光る、アプリが動く)
4コマ目: 訪れた「超最高」な変化(親子の会話が弾み、明日もやろうと笑い合う)
多くの新規事業担当者は、2コマ目のスペックや3コマ目の機能説明に偏ってしまう。しかし、顧客が対価を払うのは「4コマ目の変化」に対してである。
「1コマ目の『負の状態』と4コマ目の『超最高の状態』の落差が大きければ大きいほど、その事業は強い。ただ『課題が解決した』だけでは足りない。『最高、いや超最高』と言えるほどの感情の動きを定義できるか。やる気ペンにおける4コマ目は、単に宿題が終わることではなく、親子の信頼関係が深まる瞬間でした」
「引き算」の定義:何を測り、何を測らないか
コンセプトが固まった後、技術的な壁が立ちはだかった。「やる気」という曖昧な概念を、どうデジタルで定義するかだ。
エンジニア的な発想では「何文字書いたか」「正答率はどうか」「ペンの角度は正しいか」と、細かく分析したくなる。実際、中井氏も当初は高度な解析を研究していた。しかし、それは子供にとって「楽しい」ことだろうか。
「子供がニコッとする瞬間は、もっと単純なはずだ」。中井氏は物理学科出身のバックグラウンドを活かし、やる気の定義を極限まで削ぎ落とした。
結論は、「ペンが立って動いているか、あるいは考えている時の微細な振動があるか」。これだけだ。
「ペンが倒れていれば休んでいる。立って振動していれば、書いていなくても頭は動いている。これを『やる気』と定義しました。こうすることで、データ量は驚くほど小さくなり、電力消費も抑えられ、低コストで小型なアタッチメントを実現できたのです」
技術をひけらかすのではなく、ユーザーの「心地よい体験」のために技術を引き算する。これこそが、アナログ企業がIoTで成功するための勘所といえる。
共創型開発:プロセスを公開し、ファンを開発に巻き込む
「やる気ペン」のもう一つの特徴は、開発プロセスの透明性だ。大手企業であれば、発売直前まで情報を秘匿するのが通例だが、中井氏は開発着手段階でプレスリリースを出し、クラウドファンディングを実施した。
「世界初」といった自尊心を捨て、ユーザーと一緒に作る道を選んだのだ。クラウドファンディングで「商品企画会議に参加する権利」を購入した親子からは、容赦ない批判が飛んできた。
「こんな演出じゃ、子供は2日で飽きるよ」
こうした生々しい声から、アプリ内の「すごろく」形式の演出や、学問の多様性を感じさせる「アイテム収集」機能が磨かれていった。ユーザーは単なる購入者ではなく、プロダクトの「共犯者」となったのだ。
横展開のロジック:子供から大人へ、本質的な価値の転用

「しゅくだいやる気ペン」がヒットして数年。SNS上で意外な現象が起き始めた。大人の資格受験生やリスキリングに励む層が、子供用のペンを使って自分の努力を可視化していたのだ。
普通なら「子供用として作ったので……」とスルーするところだが、中井氏はここに次の事業の種を見出した。
大人へのインタビューで見えてきたのは、「大人の努力の孤独さ」だった。 「子供には親がいるが、大人の勉強は誰も褒めてくれない。1%の成長を実感できずに、7割の人が挫折していく。大人のターゲットにおける4コマ目は、『今日も一歩進んだ。安心して眠れる』という自己肯定感だったのです」
こうして生まれた「大人のやる気ペン」は、ハードウェアの形状こそ大人向けに洗練させたが、本質的な提供価値は変わっていない。「書く努力を可視化し、孤独な戦いを支える」こと。大人の場合は、親の代わりに「ネットワーク上の仲間の存在」を感じられる機能を厚くした。
顧客の“超最高”を設計せよ
コクヨの「やる気ペン」の物語が私たちに突きつける問いは、極めてシンプルだ。あなたの新規事業は、顧客の「超最高」を設計できているだろうか。
多くの新規事業は、「どんな技術を使うか」「どんな機能を実装するか」から始まってしまう。しかし、やる気ペンが辿った道は真逆だった。起点にあったのは、スペックでも社会課題でもない。顧客の心が動く、たった一瞬の感情変化だった。
ガミガミ怒ってしまう親が、子どもの努力を見て思わず笑顔になる瞬間。
誰にも褒められない大人が、「今日も一歩進んだ」と安心して眠れる夜。
中井氏が設計したのは、「課題が解決された状態」ではない。
人が前向きに変わる、“超最高”の瞬間そのものだった。
新着記事
-
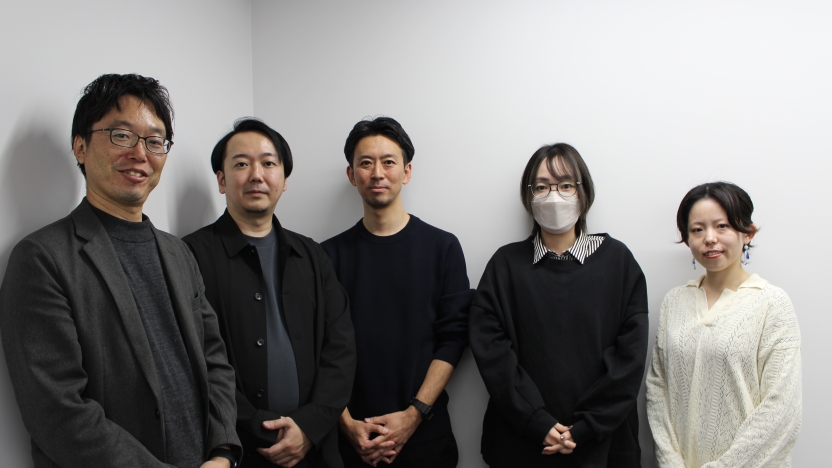 「言葉にできない感情」を、曖昧なまま受け止める 感情を色で記録するアプリ「iroai」開発チーム が1年半かけて見つけた、小さくて確かな手応え2026.02.02
「言葉にできない感情」を、曖昧なまま受け止める 感情を色で記録するアプリ「iroai」開発チーム が1年半かけて見つけた、小さくて確かな手応え2026.02.02 -
 “超最高”を設計せよ──顧客の心を動かすコクヨ「やる気ペン」開発物語2026.02.02
“超最高”を設計せよ──顧客の心を動かすコクヨ「やる気ペン」開発物語2026.02.02 -
 【3月31日(火)応募締め切り】ごみ削減ビジネスアイディアコンテスト20262026.02.02
【3月31日(火)応募締め切り】ごみ削減ビジネスアイディアコンテスト20262026.02.02 -
 【BooSTAR】 内閣府からゲストが登場! 政府が推す「スタートアップ育成5か年計画」の現在地2026.01.30
【BooSTAR】 内閣府からゲストが登場! 政府が推す「スタートアップ育成5か年計画」の現在地2026.01.30 -
 【BooSTAR】「日本政府が進める!スタートアップ・エコシステム 2026年のビジネスチャンスを徹底予想!」1月18日(日)午前10時放送2026.01.18
【BooSTAR】「日本政府が進める!スタートアップ・エコシステム 2026年のビジネスチャンスを徹底予想!」1月18日(日)午前10時放送2026.01.18 -
 連続起業は「点」ではなく「直線」だ。技術と資本を循環させる“森”の経営論2026.01.16
連続起業は「点」ではなく「直線」だ。技術と資本を循環させる“森”の経営論2026.01.16