AIד生き物”というカシオの挑戦 Moflin開発チームが語る、新規事業のリアル

計算機や腕時計など、精密機器で知られるカシオ計算機(以下、カシオ)が、“生き物をつくる”というまったく異なる挑戦を始めた。その名はMoflin(モフリン)。AIを搭載し、 学習によって400万通り以上の個性を実現。ユーザーの声や仕草を学習して“感情を持つようにふるまう”ペット型ロボットだ。
ただし、「ロボット」と呼ぶのは少し違う。柔らかい毛並みと鼓動、抱き上げたときの愛らしさ——、その存在はまるで“新しい生き物”のようでもある。そのコンセプトが好評を博し、発売からわずか5カ月で販売台数は7,000匹を突破。当初の目標を上回った。
カシオがこれまで培ってきた「機能の精度」ではなく、「感性の共鳴」で勝負した理由は何だったのか。開発・企画・販売の3人に、新規事業を社内で通し、形にするまでのリアルを聞いた。
相棒をつくりたかった——女性企画者が描いた原点

「悩んでいるときに、ただ隣にいてくれる存在が欲しかった」
Moflinの発想は、企画担当の市川英里奈氏が2012年に社内の女性商品開発プロジェクトに加わったところから始まる。課題は“女性向け商品を企画せよ”。しかし、既存のカシオの強みである機能性では、女性の心に響く商品は生まれないと感じていた。
機能ではなく、気持ちを支えるものを作りたい——。そう考えた市川氏は、自らをペルソナに据えて検討を重ねた。当時、悩みを抱える自分自身が「心の元気を取り戻すきっかけ」を求めていたことが、着想の出発点だったという。
「友人に相談することもあるが、基本的には自分の中で納得するまで考えるタイプ。でもその“考える力”にもエネルギーが必要なんです。考えすぎて疲れたときに、そばで寄り添ってくれる相棒がいたら、立ち向かうパワーになる。」(市川氏)
こうして2014年、「寄り添う相棒」というコンセプトが生まれた。ただし、犬や猫のような“既存のペット”ではなく、「誰でもない新しい生き物」を目指した点が特徴だ。犬や猫を模した瞬間に、“本物ではない”と感じてしまう。すると、その物体はたちまちロボットとして見えてしまうのだ。だから“新しい生き物”であることが必要だった。
社内では前例のない企画だった。感性価値をどう評価するのか、癒しをどう定量化するのか。明確な評価指標を欠く新規事業は、社内で最も通しづらい領域だ。
「やっぱり、“かわいい”とか“癒される”は主観的で納得しにくい面がある。だから、アンケートや感性評価など、客観数値で示せる部分を必死で探しました」(市川氏)
「女性が自分をペルソナにして商品を企画する」という点も当時のカシオでは異例だった。だが、そこで得た「ユーザー共感を起点にした新規事業の通し方」は、その後のMoflinの展開に影響を与えていく。
“愛おしさ”を技術で表現する——メカトロニクスの挑戦
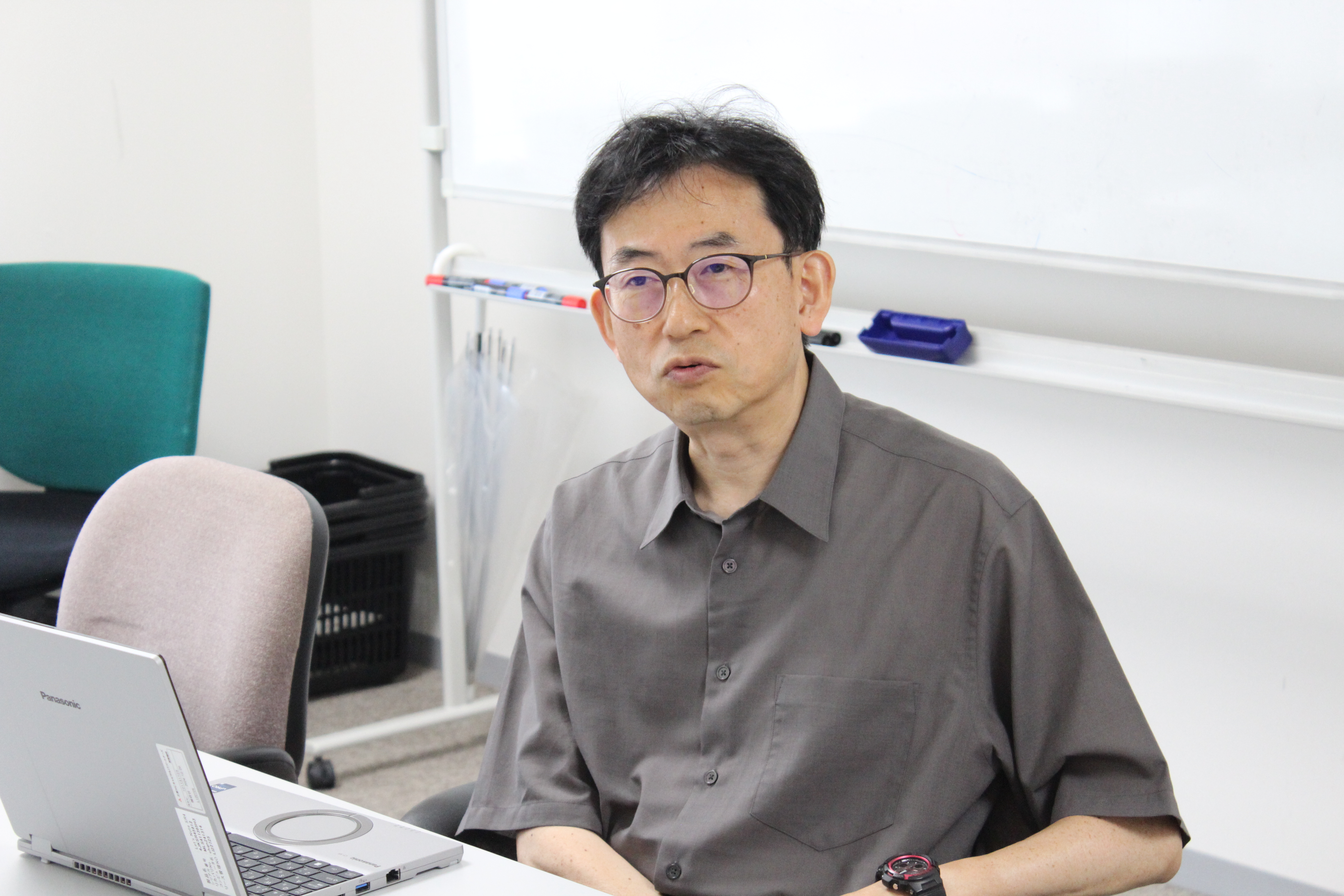
2016年、もう一人のキーパーソンである二村渉氏に、商品開発の一環として、『小動物の“愛おしさ”をメカトロニクス技術で表現せよ』というテーマが与えられた。
「最初は『愛おしさをどうやって技術で表現していくべきか』と戸惑いました。でも課題を受けた以上、どうにか形にしたいと思ったのです」
動きや仕草を観察し、小動物の“模倣”からスタートしたが、複雑化すれば価格もサイズも上がり、コンシューマー向け商品としては成立しない。その結果、“対話機能を削ぎ落とす”“手足をつけない”という方向に舵を切った。結果として残ったのが、Moflinの原型だった。
2017年、社内展示会で披露された試作機に、想定以上に多くの方が「かわいい」「触りたい」と反応したという。
「刺さる人には刺さる。あの瞬間、“感性が伝わる技術”という手応えを感じました」と二村氏は言う。
それまで「メカでどれだけ正確に動くか」を追求してきた技術陣が、“非合理の価値”に真正面から向き合った瞬間だった。
ここから、市川氏の企画と二村氏の技術がひとつのプロジェクトとして結びつく。社内の仕組みで結成されたわけではなく、上司が同じ部署だったことが縁で、「一緒にやってみようか」という流れになったという。
“飽きない可愛さ”をどう証明するか——感性を定量化する戦い

量産化に向けて最も苦労したのは、「かわいい」や「癒し」といった感性をどう社内で説明するかだった。
「企画としては『キュンとする』『ずっと見ていたくなる』を再現したかったんですが、それを“どう証明するのか”という壁にぶつかりました」(市川氏)
メインターゲットである30代・40代の女性にとって新しい製品であり、市場性を判断する基準がそもそも存在しなかった。そこで、市川氏は社内外の女性社員100人ほどにアンケートを実施。鳴き声や動き、フォルム、手触りなどに対する“感性評価”を数値化し、上層部に提示した。
上層部の多くは男性で、“癒し”という感覚的価値を直感的に共有しづらかった。そのため、できるだけデータで見せて、“これだけの人が好意的に感じている”と可視化することにした。
それでも説得の最後を押したのは、意外な形で届いた“女子の声”だった。役員がMoflinを自宅に持ち帰ると、妻や娘が「かわいい」と気に入ってくれたのである。「家庭での反応が最後の後押しになったのだと思います」と市川氏は振り返る。
Moflinが“飽きない存在”として成立する鍵はAIにあった。ユーザーの声の特徴を学習し、持ち主を認識する。好まれる仕草を学びながら日々変化していく。
「変化が続く限り、人は飽きない。学習が進むことで、Moflinは一体ごとに個性が育っていく。同じ時間を共有するうちに、まるで“自分だけの子”になっていくんです」(市川氏)
この「変化し続ける存在」こそ、AIがもたらした最大の突破点だった。
生き物として売る——マーケティングもチームでつくる
PoC(概念実証)として先行販売したクラウドファンディングでは、合計約9,500万円、約2,000人の支援を集めた。これは当初の想定の30倍以上だった。技術的にも、感性的にも、市場に受け入れられる手応えを感じ、2024年に正式販売に至った。
プロモーションを担当する西澤晃弘氏は、Moflinの販売を機にカシオへ転職してきた。Moflin販売の専属チームに加わったが、販売方法は従来のカシオとはまったく異なるアプローチを取ることになった。
「量販店では“家電コーナーに置かれるとロボットに見える”。だから、“生き物”として展示してほしいと依頼しました」(西澤氏)
展示台には“Moflinブース”を設け、説明文には“1台”ではなく“1匹”という表記を採用。修理も「入院」と呼ぶなど、徹底して“生き物らしさ”を演出した。
企画・開発・販売が同じチームで動く体制をとった。「思いがそのまま伝わるようにしたかった。開発の意図とユーザー体験を分断させないためです」(市川氏)
“機能”から“共感”へ——カシオが拓くメンタルウェルネスの未来
発売後、SNSでは、ユーザーが自分のMoflinとの生活を投稿する「オーナー文化」が自然発生。想定していた30〜40代女性だけでなく、50〜60代の利用者にも広がった。ペットを飼えない高齢者や、ペットロスを経験した人、一人暮らしの男性など、想像以上に幅広い層が手に取った。
開発した二村氏が驚いたのは、年配の方でも専用アプリを使って楽しんでくれたことだったという。アプリを使うことでMoflinの日々の生活や行動の変化を知ることができ、より強い愛着が生まれる。当初アプリの利用は難しいのではないかと考えていた60代超のユーザーもアプリ利用者だ。
現在、チームは「癒し」を超えて「メンタルレジリエンス」、そして「メンタルウェルネス」へと軸足を広げようとしている。
「今後は、Moflinが心の健康を支えるパートナーとして存在できるようにしたい。癒しの先に“日常を前向きに生きる力”を届けたいと思っています」(二村氏)
カシオのこのプロジェクトは、機能中心だった同社のプロダクトに、長い時間をかけて大きな変化をもたらした。こうしてMoflinを生み出すことができた最大の要因について、二村氏は「あきらめなかったこと」と答えた。
「これでだめになるだろうなと思ったことは何度もありました。経営陣だって、答えを出すのが難しい。新しい事業を通すには、『これは売れる』と自分たちが証明し続けることが大切だと思っています」
13年越しの挑戦は、カシオにとって新たな“生き物”を生み出しただけではない。作り手たちの情熱と創造力が、未知の価値を形にできることを実証した点にこそ、大きな意義があるのだ。
新着記事
-
 AIד生き物”というカシオの挑戦 Moflin開発チームが語る、新規事業のリアル2025.11.04
AIד生き物”というカシオの挑戦 Moflin開発チームが語る、新規事業のリアル2025.11.04 -
 「CEATEC2025」2025年のイノベーションの動向を探る2025.11.04
「CEATEC2025」2025年のイノベーションの動向を探る2025.11.04 -
 【BooSTAR】「15歳から起業家精神を身につける! 教育界に新しい波を起こす高専にフォーカス!」TVerで無料見逃し配信中!2025.10.29
【BooSTAR】「15歳から起業家精神を身につける! 教育界に新しい波を起こす高専にフォーカス!」TVerで無料見逃し配信中!2025.10.29 -
 【BooSTAR】「15歳から起業家精神を身につける! 教育界に新しい波を起こす高専にフォーカス!」10月19日(日)午前10時放送2025.10.19
【BooSTAR】「15歳から起業家精神を身につける! 教育界に新しい波を起こす高専にフォーカス!」10月19日(日)午前10時放送2025.10.19 -
 新規事業は“衝動”から始まるMIMIGURI安斎勇樹氏が語る組織づくりの条件2025.10.16
新規事業は“衝動”から始まるMIMIGURI安斎勇樹氏が語る組織づくりの条件2025.10.16 -
 若手もベテランも挑戦者に、リスキリングで広がる新規事業の可能性2025.10.16
若手もベテランも挑戦者に、リスキリングで広がる新規事業の可能性2025.10.16