新規事業は“衝動”から始まるMIMIGURI安斎勇樹氏が語る組織づくりの条件

新規事業は「アイデア勝負」だと思われがちだ。だが現場を見てきたMIMIGURI代表・安斎勇樹氏は「失敗の多くはアイデアの質ではなく、組織が挑戦を支えられなかったことに起因する」と語る。大企業の誤解、良いチームの条件、そして個人が挑戦し続けるために必要な“効力感”とは何か。数々の現場を支援してきた安斎氏の知見から、新規事業を生む組織づくりのヒントを探る。
“アイデア不足”よりも深刻な課題
安斎氏によれば、大企業の新規事業が失敗する要因として「アイデアの質」は実は大きくない。むしろ「社内から十分な支援が得られなかった」ことが主要因として挙げられるという。それにもかかわらず、多くの企業は「アイデアを出しやすくする仕組みづくり」に注力しがちだ。だがそれでは効果が薄い。重要なのは「応援し合える関係性」をいかに組織に根づかせるかである。
典型的な誤解の一つは「イノベーション=これまでにない全く新しいこと」と捉えすぎる点だ。自社事業に関わらないアイデアを募った結果、「なぜこの会社がやるのか」という問いに答えられず却下される——。こうした場面が繰り返されると、挑戦者は離脱してしまう。安斎氏は「『自社の資産を生かしつつ、既存市場ではないところにおいて、自分がやりたいことに挑戦する』というバランスの良い状態を見定めないといけない」と語る。
新規事業に対する会社の判断が、カルチャーを変えることもある。京セラで実施された社内新規事業プログラムがある。参加者が立ち上げたアレルギーミールキット「matoil(マトイル)」は、京セラの既存事業とシナジーがほとんどなかった。それでも社長がGOを出したことで、「京セラは本気で個人の挑戦を応援する」というカルチャー改革の象徴になった。必ずしも既存事業との結びつきだけではなく、カルチャー醸成を目的に評価する選択もあるのだ。※1
※1引用元:https://www.cultibase.jp/videos/8939
良いチームをつくるのは“衝動”の所在
では、新規事業にとって「良いチーム」とはどのような姿か。安斎氏は「誰がオーナーシップを持っているかが明確であること」と語る。
「強い衝動を持った一人の存在に共感が集まり、周囲がその人を推すように支えるチームが強い。変にフラットすぎると、学級会のように丸まったアイデアしか残らない」
京セラの事例でも、アレルギーで修学旅行に参加できなかった個人の体験が出発点となった。その当事者性に共感が集まり、事業化に至った。
新規事業が長い“うまくいかない時期”を乗り越えるには、このように「推し活」に近い形で衝動を支える仲間の存在が不可欠なのだ。
一方、失敗するチームの典型は「撤退の判断が拙い」ことだ。事業は改善とピボットを重ねれば成功する可能性があるにもかかわらず、短期間で「うまくいかない」と判断してしまう。経営層と現場チームの対話不足により、暗黙知や熱量が無視された撤退が行われると、挑戦そのものが萎縮してしまう。
また、チーム内の対話を重視しすぎることも問題である。全員の意見を聞き入れるうちに事業へのこだわりが薄まり、凡庸なアイデアに収斂してしまう。安斎氏は「最初にオーナーが持っていたこだわりを言語化し、チームで合意しておくことが重要だ」と指摘する。これにより改善や批判を受けても、立ち戻る軸を失わずに済む。
文化を耕し、伴走する——MIMIGURIの三つの関わり方
MIMIGURIが新規事業に関わる際は、主に3つのパターンがある。
カルチャー改革・人材育成:新規事業が生まれやすい土壌をつくる。
アイデアを形にする支援:調査データを用いたワークショップを行うなど、事業の種を見つける。
事業立ち上げに伴走:すでに事業テーマが決まっている場合、チームの一員としてブランド開発まで共創する。
たとえば、自動車部品の開発・製造を手掛ける東海理化の新規事業だったゲーミングブランド「ZENAIM(ゼンエイム)」の立ち上げは象徴的な事例だ。作りたいものへのこだわりは初めからはっきりしていたため、その内発的な動機に沿ったチームビルディングを行い、議論を重ねた。
そうして、eスポーツチームなど多様なステークホルダーと共に「本当に幸福なゲーム体験を(Well Gaming)」というブランドDNAを策定。ブランディングまで伴走し、事業化を後押しした。※2
「アイデアを発散するだけなら生成AIでもできますので、今はカルチャー改革や実行力の伴走が求められています」と安斎氏は語る。
※2引用元:https://mimiguri.co.jp/ayatori/works/zenaim/
挑戦を続けるには“効力感”の設計がカギ
大企業で個人が挑戦し続けるには、「自分の意見が反映される成功体験」が欠かせない。制服のデザインを変更するときに社員の声を反映する、チーム単位での振り返りを業務改善につなげるなど、小さな変革を積み重ねることが重要だ。
安斎氏は「挑戦を続けられるかどうかは“効力感”にかかっている」と指摘する。人は自分の行動が組織に反映されると感じられなければ、やがて挑戦をやめてしまう。選挙の投票率が「自分の一票で結果が変わる」と信じられると上がるのと同じである。
「自分の挑戦も意味がある」という小さな学習の積み重ねこそが、経営学で言う「組織学習」に他ならない。安斎氏は「組織として学ぶプロセスがなければ、いきなりイノベーションは生まれない」と強調する。日常的な効力感の設計が、新規事業を自分ごととして挑む土壌をつくるのだ。
MIMIGURIは「創造性の土壌を耕す」というスローガンを掲げているが、既存事業に創造性を宿すという“土づくり”はその第一歩である。品質維持が求められる既存事業でも、個人がこだわりを発揮し、意味づけを工夫することはできる。そうした積み重ねが新規事業に挑む力となる。
そして新規事業担当者へのメッセージとして、安斎氏はこう強調する。
「成果にコミットするのも大事だが、それ以上に『自分の学びの機会』として楽しむことが大切。周囲の声に丸め込まれず、自分の衝動を貫いてほしい」
新着記事
-
 【BooSTAR】「日本政府が進める!スタートアップ・エコシステム 2026年のビジネスチャンスを徹底予想!」1月18日(日)午前10時放送2026.01.18
【BooSTAR】「日本政府が進める!スタートアップ・エコシステム 2026年のビジネスチャンスを徹底予想!」1月18日(日)午前10時放送2026.01.18 -
 連続起業は「点」ではなく「直線」だ。技術と資本を循環させる“森”の経営論2026.01.16
連続起業は「点」ではなく「直線」だ。技術と資本を循環させる“森”の経営論2026.01.16 -
 学生起業は当たり前の選択肢へ─新たな時代の教育が拓く、起業という新しいキャリアの入口2026.01.16
学生起業は当たり前の選択肢へ─新たな時代の教育が拓く、起業という新しいキャリアの入口2026.01.16 -
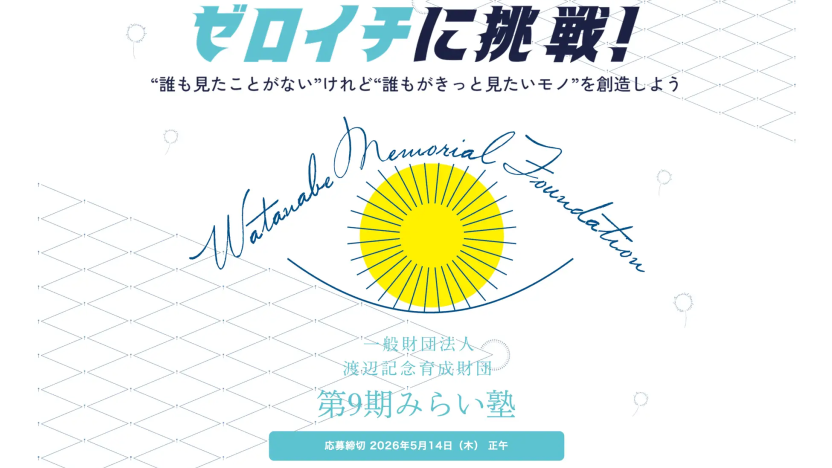 "誰も見たことがない"けれど"誰もがきっと見たいモノ"を創造したい!そんなゼロイチへの挑戦を応援する【第9期みらい塾】の募集開始2026.01.16
"誰も見たことがない"けれど"誰もがきっと見たいモノ"を創造したい!そんなゼロイチへの挑戦を応援する【第9期みらい塾】の募集開始2026.01.16 -
 NFTブームのその先へ。スタートバーンが描く「価値の構造革命」2026.01.08
NFTブームのその先へ。スタートバーンが描く「価値の構造革命」2026.01.08 -
 “実装力”を武器に、未来をつくる。 清水建設「NOVARE」が挑む、イノベーションの現在地2026.01.08
“実装力”を武器に、未来をつくる。 清水建設「NOVARE」が挑む、イノベーションの現在地2026.01.08

