若手もベテランも挑戦者に、リスキリングで広がる新規事業の可能性

若手もベテランも、新しい挑戦の担い手になれる。スキルを学び直し、人を磨き直す「リスキリング」は、単なる人材育成にとどまらず、新規事業を生み出す力へと変わりつつある。安定した企業ほど変化の必要性を見失いがちな中で、いかにして社員を挑戦者に変え、組織を前に進めるのか――。
その答えの一端を示しているのが、石川県加賀市に本社を置く石川樹脂工業だ。漆器を祖業に、かつては大手チェーン向けの食器や仏具などを手がける「利益を確保しづらい下請け的ポジション」にあった同社は、リスキリングを全社的に推進することで、自社ブランド「ARAS(エイラス)」を立ち上げ、いまや売上の約8割を占めるまでに成長させた。
リスキリングが人を変え、会社を変え、新規事業を育てていく。その歩みは、多くの企業にとって示唆に富むものである。
家業を継ぎ、人を磨き直す

石川樹脂工業の強みは、金型から成形、塗装、印刷、梱包、出荷までを担う一貫生産体制にある。分業が当たり前の業界で「できないとは言いたくない」という父の信念が、幅広い技術を自社に蓄積させてきた。
その背中を見て育った石川勤氏は、東京大学工学部を卒業後、P&Gジャパンで財務経理を9年間経験した。昇進の機会もあったが、「ものづくりをしたい」という気持ちと、父の情熱に惹かれ、帰郷を決断した。
「小さな会社だからこそ、自分で企画して突き詰められる。一方で、自分の付加価値を目に見える形で出していかないと仕事が回らない。社員のモチベーションの高さに、私自身大きな学びがありました」と振り返る。
だが、戻った会社の現場には50年前の機械が並び、作業は人手に依存していた。海外で最新設備の工場を数多く見てきただけに、日本のものづくりが後れを取っていることを痛感させられた。
最新設備を導入しても、それを動かせる人がいなければ意味がない。石川氏が選んだのは、現場のベテラン社員をリスキリングさせる道だった。産業用ロボットメーカー大手のファナックと協働し、社員たちはゼロから産業用ロボットのプログラミングを学んだ。半年以上の挑戦の末、金型の取り出しや加工、整列といった工程が自動化された。
「最初はプログラムの立ち上げに5時間かかっていたのが、今では20分でできるようになりました」
社員たちは、かつて触れたことのない技術に挑み、できないことをできることに変えていった。互いに教え合う姿勢も生まれ、学ぶことが会社のカルチャーとして根づいていった。
そうして同社の新規事業として生まれたのが、「1000回落としても割れない」「環境にやさしい新素材」を掲げる新食器雑貨ブランド「ARAS」だ。単なる新規事業ではなく、デジタル技術があってこそ実現したブランドだった。
石川氏が入社した当時、金沢市のデザイン事務所 secca と出会い、「樹脂の新しい価値提案」を目指して共同で立ち上げたのがARASである。特徴的な波打つような形状は、石膏でモックを作り、3Dスキャンした後にデジタル上で修正し、金型へと落とし込むことで生まれている。
もともと同社は早くからCADや金型分野でデジタル化を進めていた。そのため社員が新しい3Dデジタル技術に取り組むことにも抵抗は少なく、リスキリングを自然に受け入れる素地が整っていた。
技術者がマーケ担当に転向、新規事業の成長が加速
もう一つの転換点は、販売の場にあった。コロナ禍で業務用需要やOEMが激減し、自社ブランド「ARAS」を伸ばさなければ会社は立ち行かなくなる。Amazonでの販売強化は避けられない挑戦だった。
その時、石川氏が白羽の矢を立てたのは、CAD設計を担当していた一人の若手社員だった。彼女はCAD業務ではミスが目立ったが、動きが早く、手数をこなすことを得意としていた。石川氏は、その特性をこう見抜いた。
「数字の分析が苦にならず、行動量を重ねられるタイプでした。本人も『やりたいです』と答えたので任せました」
CADは正確さを求められるが、デジタルマーケティングはPDCAを素早く回すことが重視され、多少のミスは許容される。ゼロからの挑戦ではあったが、適性を信じて配置転換を決断した。結果、マーケティング施策は功を奏し、売上は3倍に拡大した。設計図面に向き合っていた社員が、広告運用や販売データの世界で試行錯誤を重ね、成果を積み上げていったのである。
リスキリングの積み重ねにより、事業は明確に上向いた。だが、学び直したのは社員だけではない。石川氏自身もAmazon販売やロボット導入の初期段階から手を動かし、「社員に学べと言う前に、経営者自身が学ばなければならない」と自らリスキリングに取り組んだ。
「リスキリングは終わりのないゲームのようなもので、やるからには覚悟が必要です。新しい技術が次々と出てくるので、私自身も常に学び続けています」と語る石川氏は、現在は生成AIの活用を研究している。
社員と経営者がともに未知の領域に挑み続ける――その積み重ねが、同社の変革の原点となった。売上は回復し、社員数も増加。全社的なリスキリングの実践が、会社を確実に成長へ導いた。
「成果に結びつかないリスキリングは意味がない。それは趣味でしかない。成果に結びつけるからこそリスキリングだと思っています」
謙虚さと貪欲さが未来をつくる
リスキリングが成功する条件について、石川氏ははっきりと語る。
「新しいことに対する貪欲さと、過去の成功体験を否定できる謙虚さ。この二つが揃えばうまくいく。逆にそれがなければ難しい」
中小企業なら経営者自身が、大企業なら経営層と管理職層が、この姿勢を持って挑む必要があると強調する。あるチームだけが取り組んでも、会社全体の生産性を引き上げるのは難しい。特に安定した会社では「リスキリングをしてもしなくてもよい」となりがちで、変化の必要性に対する切実さが欠けやすいという。
その視線の先にあるのは、自社の成長だけではない。地域や産業全体の未来だ。
「加賀市は消滅可能性都市で、20年後には生産人口が半減する予測があります。古い機械と高齢化した人材に依存する日本の中小製造業は限界にきている。だからこそ、地元で生まれた『ARAS』のような新規事業や、リスキリングによる企業変革を通じて、地域や日本のものづくりの“未来の誇り”になりたいと考えています」
石川樹脂工業の取り組みは、社員一人ひとりの学び直しから始まり、会社を変え、地域の未来を変える挑戦へと広がっている。リスキリングは単なるスローガンではなく、成果を生み出す具体的な実践であることを、この企業の歩みは示している。
変化に挑む勇気と、過去を手放す謙虚さ。未来を切り拓くヒントは、そこにある。
新着記事
-
 【BooSTAR】「日本政府が進める!スタートアップ・エコシステム 2026年のビジネスチャンスを徹底予想!」1月18日(日)午前10時放送2026.01.18
【BooSTAR】「日本政府が進める!スタートアップ・エコシステム 2026年のビジネスチャンスを徹底予想!」1月18日(日)午前10時放送2026.01.18 -
 連続起業は「点」ではなく「直線」だ。技術と資本を循環させる“森”の経営論2026.01.16
連続起業は「点」ではなく「直線」だ。技術と資本を循環させる“森”の経営論2026.01.16 -
 学生起業は当たり前の選択肢へ─新たな時代の教育が拓く、起業という新しいキャリアの入口2026.01.16
学生起業は当たり前の選択肢へ─新たな時代の教育が拓く、起業という新しいキャリアの入口2026.01.16 -
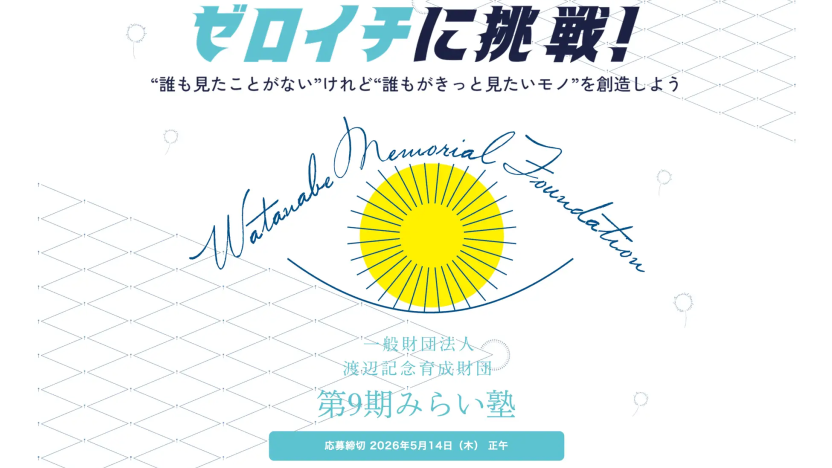 "誰も見たことがない"けれど"誰もがきっと見たいモノ"を創造したい!そんなゼロイチへの挑戦を応援する【第9期みらい塾】の募集開始2026.01.16
"誰も見たことがない"けれど"誰もがきっと見たいモノ"を創造したい!そんなゼロイチへの挑戦を応援する【第9期みらい塾】の募集開始2026.01.16 -
 NFTブームのその先へ。スタートバーンが描く「価値の構造革命」2026.01.08
NFTブームのその先へ。スタートバーンが描く「価値の構造革命」2026.01.08 -
 “実装力”を武器に、未来をつくる。 清水建設「NOVARE」が挑む、イノベーションの現在地2026.01.08
“実装力”を武器に、未来をつくる。 清水建設「NOVARE」が挑む、イノベーションの現在地2026.01.08

