日本発ユニコーンを育てる―Plug and Play Japanが挑む新ファンドの狙い
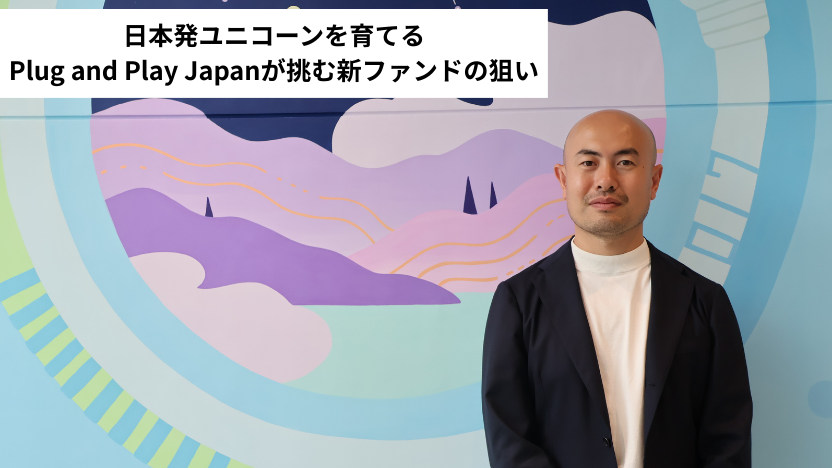
米シリコンバレー発のアクセラレーター/VCであるPlug and Play。その日本法人であるPlug and Play Japanが、日本発ユニコーン創出を掲げた独自ファンド「Plug and Play Japan Fund I」を立ち上げた。ファンド組成の背景や狙いについて、日本ファンドを主導している同社Partner, Head of Venturesの馬静前氏に話を聞いた。
「他国よりも少ない」投資額、馬氏が抱いた危機感
現在、日本に存在するユニコーンは十数社にとどまり、米国や中国、さらには韓国やインドに比べても著しく少ない。海外での認知度も限られており、国際的なスタートアップ・エコシステムの中で日本の存在感は希薄だ。そんな中、「Plug and Play Japan Fund I」について、馬氏は「最大の目的は、日本発のユニコーン企業を育成することです」と強調する。
「当社経由で世界に通用する企業を育てたい」——。その思いは、単なるファンドのリターン追求にはとどまらない。雇用創出や生産性向上、エコシステムの活性化といった経済全体への波及効果、さらにはグローバル資本や人材の流入促進など、多層的な意味を持つからだ。

Plug and Playは世界60拠点以上に展開し、現地の大手企業や投資家と深いネットワークを築いてきた。その中で日本市場は「米国に次ぐ重要マーケット」と位置づけられている。シリコンバレーには数多くの日本企業がコミットしており、オープンイノベーションや新規事業開発への関心は高い。にもかかわらず、日本のベンチャー投資規模は依然として数千億円にとどまり、欧米やアジアの他国と比べても見劣りする。
馬氏自身、前職で海外・国内双方の投資を経験した。その中で痛感したのが「日本は市場規模も技術力もあるのに、なぜ海外で存在感を示せないのか」という現実だった。隣国の韓国やシンガポールが国際的に成功事例を生み出す一方で、日本からはほとんど出ていない。「スタートアップ投資金額がGDPに占める割合はG7中最下位」という事実に、投資家として強い危機感を覚えたという。
「とりあえず米国」からの脱却、最適市場に伴走
日本のスタートアップが海外で成功事例を生み出せない要因の一つに、現地のエコシステムにコミットできていないことがあると馬氏は指摘する。
従来の日本のVCは「海外拠点を置いたものの十分に機能していない」という課題を抱えてきた。駐在事務所を設けても、現地のスタートアップや投資家からは新参者と見なされ、十分な連携に至らないことが多い。結果として「海外に行きたい起業家はいても、伴走できる支援者がいない」状態が続いていた。
Plug and Playが掲げるのは、それとは異なるアプローチだ。世界各地で20年以上にわたり築いたネットワークを基盤に、現地チームがスタートアップを直接支援する。「我々の支援の主役は現地チームです。海外の投資家に直接つなぐことができるなど、現地で長年築いた信頼関係を活用できる点が決定的に違います」と馬氏は語る。
この仕組みによって、アメリカだけでなく、欧州、東南アジア、中国など、それぞれの市場に最適な展開を伴走できる。従来の「とりあえず米国へ」という一律の戦略ではなく、各業界や技術に応じた柔軟な海外展開を支援する点が、Plug and Play Japanファンドの大きな特徴である。
Plug and Play Japan Fundの全貌
今回のファンド規模は数十億円。これまでの1,000万円前後の小口投資から一歩踏み込み、5,000万〜1億円規模のリード投資を視野に入れる。「リードを取り、成長を後押しできる体制にしたい」と意気込む。
投資領域は限定していないが、特に注力するのは三分野だ。第一にサステナビリティ関連のディープテック。素材・エネルギー・ヘルスケアといった領域は、日本が得意とし、海外でも勝負できる余地が大きい。第二にAI。“通り雨ではなく数十年続く産業”と捉え、長期的な投資テーマと位置づける。第三はバーティカルSaaS。米国ではホリゾンタルSaaSが飽和しつつあり、日本でも特定業種に深く入り込むSaaSに大きな余地があると見る。
また、LP(出資者)に対しては、単なるリターンではなく「手厚いLPサービス」を打ち出す。大きく三つの柱がある。
第一はソーシング支援。Plug and Playが持つ国内外のネットワークを活用し、出資企業の投資候補や協業先を紹介する。第二は人材育成。CVCや事業会社ではローテーション人事が多く、投資ノウハウが蓄積しにくい。そこで出向や研修を通じて投資人材を育てる。
第三はグローバルエコシステムへのアクセスだ。世界60拠点、600社以上の大企業、8万社超のスタートアップとのネットワークに接続できる点は、他の国内ファンドにはない強みである。
「日本のLPは必ずしも高いリターンを期待しているわけではない。だからこそリターン以外の価値を提供することが重要だ」と馬氏は強調する。
Exitの多様化で資本循環を呼び込み、日本発ユニコーンへ
Plug and Play Japanのファンドの強みとして、馬氏が特に強調するのは「同社を経由することによるExitの多様化」である。現在の日本スタートアップの出口戦略は、小型IPOかM&Aに偏っている。その結果、投資資金の好循環が生まれにくい。
同社は、海外支援を通じて日本企業が海外投資家と接点を持ち、クロスボーダーでのExitを実現することを目指す。たとえば、海外の大手企業を買い手として日本のスタートアップを買収するケースや、香港・シンガポール・欧州といった米国より上場基準の緩い市場でのIPOも視野に入る。
さらに、馬氏は「セカンダリー取引」の重要性にも言及する。日本ではまだ認知度が低く、投資家の理解も十分とはいえないが、海外投資家にとっては一般的な選択肢だ。新規ラウンドがない場合でも、既存株を買うことで日本市場に投資できるため、資本循環の呼び水となる可能性がある。「セカンダリーはファンドパフォーマンスにとってメリットが大きい、LPにとってもスタートアップにとってもメリットは期待できるため、当社がその橋渡し役になる」と語る。
「国内だけでは限界がある。ユニコーンを輩出することで、海外資本や人材を呼び込み、競争力を高めたい」という言葉には、日本スタートアップの出口を世界に広げる強い意志がにじむ。
最後に、馬氏は日本の起業家へのメッセージをこう締めくくった。
「日本の技術は皆さんが思う以上に優れています。大学発を含め、ポテンシャルは大きい。怖がらずに胸を張って海外に出ていってほしい。そこには我々のように全面的に支援する投資家がいる」
Plug and Play Japanの日本ファンドは、単なる資金供給にとどまらず、グローバルネットワークを活用した伴走型支援を特徴とする。日本発ユニコーン輩出という野心的な目標は、投資家にとっては挑戦であり、スタートアップ・エコシステムにとっては大きな試金石となるだろう。

新着記事
-
 【BooSTAR】「日本のスタートアップをレベルアップさせる外国人起業家たち」TVerで無料見逃し配信中!2025.12.17
【BooSTAR】「日本のスタートアップをレベルアップさせる外国人起業家たち」TVerで無料見逃し配信中!2025.12.17 -
 【BooSTAR】「日本のスタートアップをレベルアップさせる 外国人起業家たち」12月14日(日)午前10時放送2025.12.14
【BooSTAR】「日本のスタートアップをレベルアップさせる 外国人起業家たち」12月14日(日)午前10時放送2025.12.14 -
 「飲む」から「食べる」へ。大組織から解き放った新食文化「モカブル」のカーブアウト戦略2025.12.09
「飲む」から「食べる」へ。大組織から解き放った新食文化「モカブル」のカーブアウト戦略2025.12.09 -
 【12月22日(月)応募締切】異能vation ジェネレーションアワード2025.12.09
【12月22日(月)応募締切】異能vation ジェネレーションアワード2025.12.09 -
 【BooSTAR】「経験と人脈が最大の武器! ~シニア起業の最前線~」11月23日(日)午前10時放送2025.11.23
【BooSTAR】「経験と人脈が最大の武器! ~シニア起業の最前線~」11月23日(日)午前10時放送2025.11.23 -
 FTS Journalの 2025上半期人気記事5選を一挙ご紹介2025.11.21
FTS Journalの 2025上半期人気記事5選を一挙ご紹介2025.11.21

